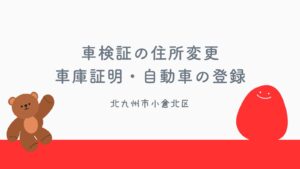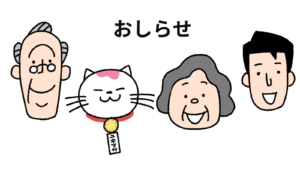【行政書士が解説】5分でわかる丁種封印制度(事業者向け)

はじめに
北九州の行政書士が、封印についてわかりやすく簡潔に解説いたします。
普通自動車の手続きには欠かせない封印についてしっかりと理解して便利な丁種封印制度をご活用ください。
封印制度について
1.封印とは?
普通自動車の後面ナンバー(リアナンバー)には、ナンバープレートを固定するために締めるボルトと一緒に封印冠と呼ばれる部品を取り付けます。
この封印冠という部品にはめ込むアルミ製のキャップのことを「封印」といいます。

2.封印の役割って?
封印の役割は主に2つです。
・運輸支局(陸運局)で手続きが行われた登録自動車であるということを公証する役割
・車両自体の盗難防止、ナンバープレートの取り外しや盗難の防止
3.封印って外していいの?
封印は、正当な理由なく外すことができません。
根拠は道路運送車両法第11条に規定があり、同条の規定に基づき道路運送車両法施行規則の第8条において正当な理由と解釈できる場合について具体的に言及がなされています。
参考:道路運送車両法第11条第5項
何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又はこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
参考:道路運送車両法施行規則第8条第3項
法第十一条第五項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は次のとおりとする。
一 自動車の整備のため特に必要があるとき。
二 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第五条第一項の規定により国土交通大臣から交付を受けた登録証書(第四十条の五第一号において単に「登録証書」という。)に記載された登録番号を表示するとき。
4.知ってましたか?封印の委託制度と4種の封印受託者
実は、日本の法令上、封印を取り付けることができるのは国土交通大臣と封印取付に関する事務の受託を受けた封印取付受託者だけです。
特にこの封印取付受託者には甲乙丙丁という区分があり、このうちの「丁」にあたるのが我々行政書士です。(厳密には行政書士会)
この4人の封印取付受託者については下記の表のようにまとめることができます。
| 受託者の区分 | 具体的な団体 | 備考 |
|---|---|---|
| 甲種受託者 | ナンバープレートの交付代行者 →標板協会が該当します | |
| 乙種受託者 | 型式指定車の新車販売業者 | |
| 丙種受託者 | 各都道府県の中古車販売協会 →JUが該当します | |
| 丁種受託者 | 各都道府県の行政書士会 |
上記の表を見て「あれ?」と思った方、さすがです。
そうなんです。実は行政書士が封印の委託を受けているわけではなく、あくまでその行政書士が所属する行政書士会が委託を受けているだけなんです。
ではなぜ各々個人の行政書士が封印を取り付けることができるのでしょうか?
5.行政書士が封印を取り付けることができるからくり「再委託」
行政書士が封印を取り付けることができるのは、各都道府県の行政書士会から「再委託」を受けているからです。
再委託というのは国土交通大臣から都道府県の行政書士会が受託した事務をさらに委託しているということです。
都道府県の行政書士会が再委託した行政書士を特に「丁種会員」と呼びます。
一定の研修等を受け、能力を認められた行政書士のみがこの事務を受託することができます。
この丁種会員については、賠償責任保険への加入+丁種封印に関する付帯保険への加入が義務付けられているため万が一のトラブルの際も安心です。
行政書士だけの特権~丁種封印~
これまでは封印の制度そのものについて解説してきましたが、ここからは行政書士の特権である丁種封印について説明します。
1.国有財産である「封印」のとてつもない威力
封印は持ってみるとわかりますが、本当にちゃっちいアルミの部品です。
しかしながらこのどこかか弱い触感とは裏腹にこの封印にはとてつもない威力が存在します。
封印は、福岡県行政書士会においては前渡し方式を採用しており、請求すれば何個でももらえます。
とはいえ取り付けていない封印は国有財産であり想像以上に厳格に管理されています。
この変哲もない封印がとてつもない威力を発揮する場面が2つあります。
まずは、ナンバープレートに取付を行ったとき。
封印冠にはめてしまったら最後、一切動かすことができなくなります。
少しでも斜めに入ってしまったらもう最後、動かすことができません。封印取付後に斜めになっているのに気づいたときはもう発狂ものです。
もう1つは、封印を1つでも失くしてしまったときです。
事務所1つが吹き飛びます。
むしろ1つ吹き飛ぶくらいで済めばいいほうです。
どうしてこんなことになるか怖すぎて言及できませんが、とてつもない威力をもっています。
2.丁種封印でできること
次に丁種封印でできることについてご紹介します。
丁種封印でできることは下記の3つです。
・出張封印
・日本全国の封印の再封印
・丁種封印再々委託
これらは上手に使えば大変便利な制度ですので、ぜひ知っていただき、お困りの方は行政書士へご相談ください。
2-1.出張封印
普通、封印の取り付けは各受託者の事業所において行うものとされており、一般的には陸運局で封印を取り付けてもらうという認識だと思います。陸運局の封印は福岡県であれば標板協会という団体がいわゆる甲種封印という権限を行使して取付をしており全国の封印を取り付けてくれます。
標板協会そこそこ万能な存在ではあるのですが2つだけ欠点があります。
それは平日の16時以降と土日祝日に関しては封印を取り付けてもらえないという点と陸運局以外の場所で封印をしてもらえないという点です。
この欠点を補うことができるのが行政書士のもつ丁種封印です。
行政書士に関しては「ユーザーの利便に資する」という大義名分があるため時間と場所の制約が原則的にありません。
ご指定の場所でいつでも、どこでもお伺いし封印の取り付けを行うことができます。
元々は自動車の登録手続きを行政書士が行ったものに限定されていたのですが令和6年よりその制限もなくなり、例えば車屋さんやユーザーさんが登録をした自動車であっても行政書士の封印を使うことができます。
1つだけ欠点があるとすれば、全国の封印を取り扱うことができるわけではないという点です。
福岡県行政書士会の丁種会員については福岡県の封印はもちろん、山口県と大分県、佐賀県の封印を取り扱うことができます。
上記以外の地域の封印が必要な場合は、その地域の行政書士さんから再々委託を受ける必要があります。
この再々委託については、後ほどご説明させていただきます。
ポイント
・丁種封印には場所・時間の制限がありません。
→いつでもどこでも封印の取り付けが可能です。
・登録と封印が分離されているため、車屋さんが登録した自動車であっても行政書士による封印の取り付けが可能です。
2-2.再封印
自動車の板金や整備を行う事業者様で、まれに封印の取り外しを伴う整備を行うことがあります。具体的には、後面ナンバーを取り外す必要がある板金や整備のことです。この場合、事情が止んだ後、速やかに封印の取り付けを陸運局で行わなければなりません。
封印を外してしまっている以上、回送ナンバーや陸送車を利用しなければ公道を走行することはできません。
このようなときに行政書士が役に立ちます。
丁種封印では、再封印に関してのみ運輸支局等から日本全国の封印の払出を受け再封印を行うことができます。
例えば、鹿児島ナンバーの板金を請け負い再封印が必要になった場合、丁種会員である行政書士にご相談いただければ、鹿児島の封印を福岡支局等で受領し、再封印を行うことができます。
つまり、回送ナンバーの取り付けや陸送車の準備などの面倒な手間なく、車を一切動かさずに再封印を行うことができます。
ポイント
・再封印については日本全国の封印を取り扱うことができます。
2-3.丁種封印再々委託
この丁種封印の中でも極めて優秀な機能の1つが「再々委託制度」です。
県外での登録や県外ナンバーの後面再交付等で封印の払出が必要になる場合に役に立ちます。
前述した「再委託」と名称が似ていてややこしいのですが、再委託は行政書士会と行政書士の間での事務の委託です。
「再々委託」というのは、丁種会員である行政書士同士の封印の事務の委託です。
つまり封印権を持っていない地域の封印でもその地域の行政書士から委託を受ければ封印を取り付けることができるわけです。
例えば、次のようなケースでこの制度が役に立ちます。
【ケース】
福岡県の北九州市で外国産の普通車の中古車販売店を営むAさんは、大阪府のユーザーに自動車が売れたため、なじみの行政書士のNに自動車の名義変更手続きの手配を依頼しました。Aさんからの依頼を受けた行政書士のNは、大阪府の行政書士Bにこの名義変更手続きを依頼することにしました。
【登場人物】
〇依頼者A (福岡県の車屋さんで行政書士のNに自動車の登録を発注した事業者様)
〇行政書士N (福岡県の行政書士で依頼者Aさんから自動車の登録手続きを受任した行政書士)
〇行政書士B (大阪府の行政書士で行政書士Nから自動車の登録手続きを受任した行政書士)
【上記のケースでの課題】
〇北九州市→大阪府に移動するため、ナンバーが変わります。
→封印の取り付けが必要ですが、福岡県行政書士会の行政書士であるNは大阪の封印権を持っていません。
上記のような状況で、この再々委託という制度が役に立ちます。
再々委託というのは、Bが登録手続きを行った自動車の封印の取り付けをNに委託することができる制度です。
本来であれば、Bから遠路はるばる大阪から福岡まで来てもらい封印をしてもらわないといけないのですが、この制度を利用することでBの代わりにNが依頼者のAさんのところに手続き完了後の書類と、新しいナンバープレートをお持ちし封印するという流れになります。
このように福岡に自動車を置いたまま、大阪での手続きを終え、無事に大阪の封印を取り付けることができるわけです。
なお再々委託より先の委託(ex.再々々委託)については禁止されています。
あくまでも再々委託先(封印を払い出してもらう方)の行政書士と再々委託元(封印を払い出した方)の信頼関係に基づく制度であり、これ以上の介入を許すと封印の紛失などトラブルのもとになるからです。
ポイント
・丁種封印再々委託は、県外登録や県外ナンバーの再交付時に封印の取付も必要になる場合に役に立ちます
・行政書士を挟むことで、自動車を動かさなくても県外の封印の取り付けが可能です。
3.裏ワザ ナンバープレート後返納
丁種封印には、先ほど説明した3つのほかに裏ワザ的な制度があります。
それがナンバープレート後返納制度です。
一定の手続きにはなるのですが、丁種封印権を持つ行政書士は、従来では前返納のナンバープレートを後返納することができます。
具体的には、住所変更によりナンバー管轄が変わった場合の変更登録、番号変更、番号変更を伴う名義変更です。
このナンバープレート後返納制度のメリットは、「手続き中も自動車を使い続けられる」という点です。
一般的に番号変更を伴う手続きのときは、手続きと同時にナンバープレートを返納するため自動車を使うことができません。
すると出退勤や日常生活で自動車を使うユーザーにとって自動車を使えないのは大変不便です。
そこで国と行政書士の信頼関係にのっとり、手続き完了後、一定期間内にナンバープレートを返納することを制約することで前のナンバープレートを返納することなく手続きを行うことができます。
なお、前のナンバープレートについては出張封印に伺った際などに行政書士が責任をもって回収し、返納しなければならないため余分にユーザー様方に手間が増えることはありません。
まとめ
つたない説明になりましたが封印制度と丁種封印について解説しました。
自動車販売店様はもちろん、整備工場や板金修理工場様などにもどんどん知っていただき利用してもらうべき便利な制度です。
封印に関するお困りごとは、北九州の行政書士の乗越にまでご相談ください。